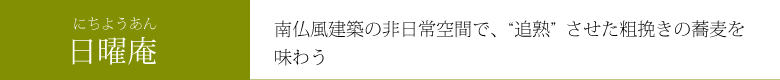

荒挽きそば -少量の水蕎麦がつく-
柴又、帝釈天近くの住宅街に
柴又にある蕎麦屋と聞いて、どんなイメージを持つだろうか。 江戸蕎麦の伝統を感じさせる蕎麦屋だろうか。はたまた下町らしく気さくな店だろうか。ところが、これから訪れる蕎麦屋さんは柴又にあるのに柴又らしからぬ店である。 そこに不思議な魅力があって、時折無性に行きたくなる蕎麦屋さんなのだ。
そんなことを考えながら都会のローカル線・京成金町線に揺られ柴又駅に着く。改札の前には「フーテンの寅さん」の銅像。 いつ来ても寅さんと記念撮影をする観光客の姿が絶えない。 参道の草団子屋を冷やかしながら帝釈天へ。 参道を歩いていると、寅さん映画の登場人物のような善人になった気がしてくるのは、この街の持つ魔力だろうか。懐かしい、下町、という言葉だけでは説明しきれない何かがこの街にはある。 そして、私にとって、この街の不思議な魅力を形成する、もう一つの源となっているのが、帝釈天近くにある「日曜庵」だ。
南仏風建物の洒落た蕎麦屋
住宅街の一角に建つのは明るい色彩の洋風建築。柴又なら和の空間という予想は快く裏切られ、外壁を淡いクリーム色で塗られた南欧風の建物である。 はじめて見たときは驚いたものだが、開店して10年。周囲の景色と馴染んできたように思う。木の扉を開けて中に入ると、店内は天井までの吹き抜けになっている。天窓があるものの目線の高さに窓はなく細長いステンドグラスがあるのみ。 照明は銅板を腐食させてできた無数の穴から洩れる灯り。 穴蔵のような異空間に入り、一瞬にして非日常の世界へと紛れ込んだ。
空間、器、料理・・・店主のセンスが光る
まずは「開運」のひやおろしを。運ばれてきたお盆の上には大きめの片口とぐい呑み、塩、信楽焼の四角い香合のような器にはちりめん山椒、細く繊細な塗り箸。選び抜かれた器の組み合わせは、これだけで一つの作品のようだ。 ちりめんを摘みながら、ぐい呑みを飲み干す。夏を越したひやおろしの豊かな味わいにほっと一息ついた。
つまみに頼んだ鴨焼きは鉄板で焼いて塩バルサミコ酢でいただく。 厚切りの岩手産合鴨はジューシーで鴨肉の旨み、甘みが口一杯に広がった。 蕎麦がきは淡い緑色が美しい。 紫蘇オイルと醤油、ワサビにつけて。 ふんわりとやさしい食感で口の中でとろける。
器が素敵だ。 分厚くダイナミックな造形の土ものが多い。 ご主人が自分で絵を描いて焼いてもらった器もあるそうだ。 空間といい、器といい、このセンスはCMカメラマンだった店主、西村宏さんならではのものだ。







